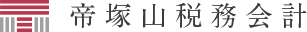ブログBLOGS
2025.03.21 遺産の共有解消の見直しについて(本文添付)
⑴遺産の共有制度については、相続人が多数のため所在不明者がいる場合や相続登記未了に伴う所有者不明の場合があるなど共有不動産の管理や処分に支障をきたしている事は従来より指摘されています。2023年4月1日の民法改正により、次のように共有物に円滑な利用が図られることとなっています。
⑵共有物利用円滑化の民法改正内容 ①軽微な変更や一定期間内の短期賃貸借の設定は、共有持分の価格の過半数で決定できる。 ②管理に関する賛否を明らかにしない共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、共有持分の価格の過半数で、管理に関する事項を決定できる。 ③所在者不明の共有者がいる場合であっても、裁判所の決定を得て、他の共有者全員の同意で共有物に変更を加えることができ、さらに、共有持分の価格の過半数で、管理に関する事項を決定できる。 ④遺産が共有の場合には、共有規程の適用に関しては、法定相続分又は指定相続分により算定した持分を基準とする。
⑵共有財産の分割手法 従来からの民法においては、共有者者間の共有持分は、家庭裁判所が管轄する遺産分割手続きと、地方裁判所等が管轄する共有物分割手続きで、共有の分割手続きを行う必要でしたが、民法の改正に伴い、相続開始から10年を経過した時は、遺産共有関係の解消も含めて、地方裁判所等が管轄する共有物分割手続きのみで共有解消が可能となります。
⑶結論 裁判所は共有者の請求により、他の所在不明などの共有者の持分を、請求者に取得させたり、その共有持分を含めた不動産全体を譲渡させたりすることが可能となります。ただし、遺産共有の場合には、遺産分割の機会を保障するため、相続開始から10年を経過した時に限り、取得させたり譲渡させたりすることが可能となっています。